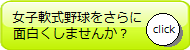takahasi
★2012年6月11日
シリーズ 指導者たち⑥
高橋町子 (元「わかもと」選手、現「ノーザンライツ」監督)
どんな人にとっても一球の重さは同じです。
男でも女でも、たとえ体が不自由な人であっても

Machiko Takahasi
昭和11年、宮城県鬼首温泉郷の出身。高校卒業後、女子企業チーム「わかもと」でプレー。昭和53年にわかもとOG中心の女子軟式野球チーム「ブルーエンゼルス」を結成。平成4年に「ノーザンライツ」を立ち上げ、現在監督兼選手。平成11年に還暦野球チーム「エンゼルス」も結成。昭和55年に東京都軟式野球連盟公認審判員となり、東京都還暦軟式野球連盟の理事兼審判員、全国高等学校女子硬式野球連盟の審判員も務めている。
(文中敬称略)
約60年前、日本に女子プロ野球や女子社会人(企業)野球があったことをご存じの方も多いだろう。高橋はその企業チームの選手として野球のキャリアをスタートし、その後は女子軟式野球チームの監督兼選手、軟式硬式の審判員として女子野球の歴史をつぶさに見てきた。野球は男のものという偏見に苦しみながらも、「野球がやりたい」という思いを貫いてきたその60数年にわたる足跡をたどりながら、高橋が学び取った指導理念をご紹介したい。
ぜんまいの綿で作ったボールから始まった野球との関わり
宮城県北部に位置する鬼首(おにこうべ)温泉郷の旅館の末娘として生まれた高橋は、幼い頃は孤独な少女だったという。両親は稼業に追われ、兄や姉にはかまってもらえず、
「いつも一人で川向こうの目標などに向かって石を投げて遊んでいました。ぜんまいの綿ボールを石垣にぶつけて遊んだりもしたんですよ。周りは深い山ですからぜんまいがたくさん採れるんですが、その綿を集めてたこ糸でグルグル巻くと、ぜんまいの綿は強いですからポーンと弾むんです。そうやって遊んでいる時が一番心安らぐ時間でした」

やがてぜんまいの綿ボールはゴムボールに替わり、男の子たちと毎日日が暮れるまで三角ベースなどで遊ぶようになった。中学では野球部に入ったが、女子は試合に出られない。しかも家族は女子が野球をすることに大反対で、
「『男みたいでみっともないからやめろ』『親の言うことを聞かないのは不良だ』って毎日のように怒られましたねえ。なんで女は野球をやっちゃいけないの? なんで不良なの? 私はただ野球が好きなだけなのにって何度悔しい思いをしたかわかりません」
そんなある日、旅館に県立古川高校の校長が泊まりに来た。そして高橋のキャッチボールの相手をしながら、「町子、おまえはな、東京さ行って野球しろ」と言ったのだ。
日本初の女子プロ野球チーム「ブルーバード」が結成されたのは昭和24年5月、高橋が中学1年生のときのこと。校長はそれを知っていたのだろう。
「うれしかったですね。野球をやりたいという気持ちを人に認めてもらったのは初めてでしたから。東京さ行ったらオラ野球がやれるんだ、東京ってどこにあるんだべがって、そればかり考えるようになりました」
岩出山(いわでやま)高校に通うようになってからは硬式野球部の練習に交ぜてもらい、初めて硬式球を手にした。その重さ、打ったときの感触、その全てに魅せられた。「私も硬式野球がやりたい」と体が震えるほど強く思ったというが、女子は試合に出ることはもちろん部員になることすら許されない。そのため誘われるままにソフトボール部に入部し、第8回の四国国体に出場した。しかしソフトボールで華々しい成績をおさめても、野球に対する思いは消えなかった。
急展開した運命。女子企業チームの入団テストに合格
高校3年の夏だった。
「たまたま出かけた古川市で『女子野球団来る。わかもと、三共』という看板を見つけたんです。あ、やっぱり校長先生が言ったとおり、東京には女子野球団があるんだと思って早速グラブを持って見に行きました。
するとわかもとの中島京子主将が『野球が好きなんですね』と話しかけてきて一緒にキャッチボールをしてくれたんです。そして『東京で女子野球のテストがあるから受けにいらっしゃい。そのときはわかもとに入りたいって言うのよ』と言われて」
12月、親戚を頼って上京し、新宿の東京生命球場でテストを受けたのである。
当時女子プロ野球はすでに社会人(企業)野球に移行しており、「わかもと」「岡田乾電池」「三共」「エーワンポマード」「京浜急行」「坂口翁(さかぐちおきな)」の6チームがしのぎを削っていた。
このテストは6チーム合同で行われ、50メートル走やキャッチボール、バッティング、ゴロの捕球などをチェックされたという。
「1月に『合格しました わかもと』なんて通知が来て、それからは家族の反対なんて耳に入りません。すぐにスプリングキャンプに合流して、卒業式のためにいったん帰郷して、またチームにもどるときは同級生たちが駅のホームに並んで蛍の光を大合唱し、『町子がんばれよー』と言って送ってくれました」
昭和30年、野球という名の翼を手に入れた少女は、新天地に向かって羽ばたいた。
女子企業チーム「わかもと」での生活
「わかもと」の合宿所は東京都世田谷区砧(きぬた)にあった。現在は駒澤大学玉川キャンパスになっているが、当時はここに工場と女子野球部の合宿所があり、合宿所には約20人の選手が暮らしていた。
「方言がなかなか直せなくて先輩に1日30回ぐらい怒られましたけど、大好きな野球が思い切りできる生活はパラダイスでした」

リーグ戦は春と秋にあり、それぞれの優勝チームが日本一をかけて争う「日本選手権」も行われ、夏は夏でトーナメント大会が開かれていた。使用していたボールは準硬式球(トップボール)だ。
パワーがあって肩が強かった高橋は入団早々レギュラー入り。ショートで三番が定位置になった。打撃は好調でどのシーズンも打率は3割を超え、本来なら首位打者争いに加わってもおかしくない成績だったが、野球に反対する家族が何かと理由をつけては家に呼びもどしたため、規定打席に届かず、無冠の帝王に終わってしまったという。
「一番の思い出は入団2年目に鬼首の人たちが高橋町子後援会を作って応援に来てくださったことです。私たちは会社の宣伝マンですから、大会がないときは日本全国を試合して回るんですが、母校の岩出山高校に遠征したとき、バス2台に分乗して駆けつけてくれたんです。私みたいな者のためにと、感動しました」
尊敬する指導者との出会いと、女子企業野球の終焉
高橋はわかもとで尊敬する指導者に出会う。島津雅男だ。昭和6年に早稲田実業学校のエースとして甲子園の土を踏み、早稲田大学卒業後は「東京鉄道局」などでプレーした人物だ。
「何度エラーしても絶対に怒らない監督だったんですよ。いつも穏やかで言葉遣いも丁寧。君にはこういう課題があるけど、こんな素晴らしいところもあるんだよと言って、みんなのいいところを引き出してくださいました。試合ってチームワークが悪ければなかなか勝てないじゃないですか。でも島津監督のもとではチームワークが乱れることは決してなく、自然と団結して勝っていくことができました。融合というんでしょうか、黙ってみんなを抱きかかえてくださるような、そんな懐の大きな方でした」
島津は昭和31年に学習院大学硬式野球部監督にも就任し、33年に東都大学野球1部リーグでチームを優勝に導くが、
「学習院の試合を見に行ったら、やっぱり私たちと同じように指導されていました。男と女で区別することはなく、どんな人にも敬意をもって接してくださいました。本当に私の野球の神様でした」
島津の指導者としてのあり方は高橋の心に深く刻みこまれ、後年「島津流」と自ら呼ぶ指導につながっていった。
さて、家族の反対に悩まされながらも充実した青春を送っていた高橋だったが、「わかもと」は昭和33年9月に解散。1年間のOL生活の後、一度は家の都合で鬼首に帰るが、昭和36年に再び上京。「お給料の額より野球部があるかどうか」で会社を選び、女子は試合に出られないことを承知で軟式野球部でプレーした。結婚出産後はバッティングセンターで日本初の女性コーチとして野球の指導にあたったという。
また「わかもと」解散後も頼まれれば他の女子企業チームに助っ人として入り、大会に出るなど、どんな状況になっても生活の中から野球が消えることはなかったのである。
その女子社会人(企業)野球だが、新しいチームができては消えしながらも昭和42年頃まではリーグ戦が行われていたが、昭和46年に最後まで残っていた「サロンパス」が解散することによって終焉の時を迎えた。同時に女子野球は表舞台から姿を消したのである。
「島津流」で作り上げた女子軟式野球チーム「ノーザンライツ」
「指導者に必要なのはまず優れた人間性で、そのあとに技術や戦術が来ると思っています。怒鳴ってばかりでは人はついてきませんし、チームワークも生まれません。また選手の欠点ばかり見る人よりも、良いところにも目を向けて伸ばしてあげる人のほうが強いチームが作れます。技術指導も、できない人であればあるほど丁寧に教える。そういう姿勢を島津監督から学びました」

その「島津流」の指導で作り上げたのが女子軟式野球チーム「ノーザンライツ」だ。
平成4年、新しいチームを立ち上げるべく地元の広報誌に「野球の好きな女性の方、ぜひご参加ください。年齢は問いません」という募集記事を出した高橋は、のっけから重大な決断を迫られることになった。68歳と70歳の女性が応募してきたのだ。
「驚きました。初心者が来ることは予想していましたけど、そんなに高齢の方が来るとは思っていませんでしたから。年齢を考えると練習中に倒れるかもしれないし、走ったら心臓が苦しくなるかもしれない。でも年齢は問いませんって言ったのは私ですから、救命技能の講習を受けて万全の態勢でやろうと。それで万が一のことがあったらしようがないと覚悟を決めました」

70歳の人はソフトボールの経験者だったが、68歳の人はボールを握ったこともない全くの初心者だったため、
「彼女だけ柔らかいボールでやろうか悩んだのですが、いや、同じチームなんだから同じボールでやろうと決めました。ただでさえメンバーの年齢の幅が広いんですから、そうでなければ同じ気持ちでボールを追いかけられないじゃないですか」
技術指導も年寄りだからと適当にすませることはなく、ボールの握り方はもちろん、グラブの使い方、投げ方、立ち方、バットの芯でボールをとらえるというのはどういう感覚かなど、必要なことは全て基本から教えた。言葉遣いも難しい専門用語ではなく、その人がわかりやすい言葉を使うように心がけた。
おかげで68歳の女性は驚くほど熱心に練習に励み、キャッチボールも最初は2メートルしか投げられなかったのが、次第に5メートル、10メートルと投げられるようになっていったという。
「進歩するスピードに差はありますけど、その人に『できてよかった、野球って楽しい』と思ってもらいたいんです。若い人でもお年寄りでも野球がやりたいというのなら、その気持ちにきちんと応えるのが指導者の務めではないでしょうか」

創部から20年たった今でもノーザンライツは75歳の高橋から、70歳の遊撃手、60歳の一塁手、中学1年生の選手まで、幅広い年齢の女性が野球を楽しんでいる。それを可能にしているのがチームワークを何より大切にする高橋の存在だ。
「野球が楽しいと思う気持ち、良いプレーをしたときの充実感は誰でも同じです。だから年齢に関係なく、みんなで仲良くやりましょうといつも言っています。そしてうまくいったときはほめ、エラーをしたときは絶対に責めない。『次捕れるよ』と声をかけてその選手の気持ちを楽にしてあげる。当たり前のことかもしれませんが、それが次のファインプレーを生み、チームワークにつながるんです。
また『人の悪口を言ったり派閥を作ったりしない』『野球をしに来ている間は人の詮索はしない』ということも話しています。
決して強くはないけれど、お年寄りや若い人たちがお互いに敬意をもって一つのボールを追いかける、こんなチームがあってもいいんじゃないでしょうか」
43歳で都軟連の審判員に。視野を広げてくれた審判の仕事
高橋は昭和55年、43歳のときに東京都北区初の女性審判員となった。女子は選手として認められず、全日本軟式野球連盟の大会に出られなかったため、なんとかしてきちんとしたかたちで野球に関わりたいと思ったからだ(全軟連が中学生以上の女子の出場を認めるようになったのは平成6年から。学童は昭和62年から)。
審判の世界でも女子の参入を認めない風潮があったが、
「私を受け入れてくださった北区の連盟に心から感謝しています。また審判をやらせていただくことによっていろいろな人と出会い、視野がものすごく広がりました。

たとえば聴覚障害や視覚障害の方の野球があるのをご存知ですか? 目の見えない人は手をたたいてもらって音を頼りに打ったり走ったりするんですよ。また肢体不自由の方のなかには手首にボールをはさんで投げる方もいます。でもどんなに体が不自由でも、みなさん本当に生き生きと野球をしていて、そのことにすごく感動したんです。だからもっとゲームを楽しんでもらいたいと思って手話や点字の勉強もしました。
また献身的に支える心身障害学校(現在の特別支援学校)や盲聾学校の先生方とも知り合うことができて、人間の尊厳についても勉強させていただきました。特に障害者教育の草分け的存在の山崎剛先生には、一時期チームにコーチとして入っていただくほど大きな影響を受けました。
今でもノーザンライツは体の不自由な方々とよく練習をするんですが、それは障害者のみなさんのためではありますが、うちのメンバーにとっても良い人生勉強になるという、指導者としての思いがあるからです」
こうした経験を積み重ねて思うことがある。
「一球の重みは誰にとっても同じだということです。一つのボールの前に人は皆平等なんです。誰にだって野球をする権利がある。男でも女でも、たとえ体が不自由な人でも」
75歳になっても現役でいる、その姿を見てほしい
60数年にもわたって野球を続けられた理由を高橋はこう語る。
「わかもとが解散してしまったために、後援会を作ってまで応援してくださった鬼首の皆さんに恩返しができなかったからです。いつかその思いに報いたいと思ってここまでやってきました。

それともう一つ、女子も硬式野球ができる日が来るまでは絶対にやめられないと思っていたからです。高校で初めて硬式球を手にしたあの日からずっと硬式野球がやりたかった。でも硬式はおろか野球をすることすらダメダメダメと断られ続け、男の人は野球をやらせてもらえるのになんで女はだめなの? 男とか女とかいう垣根なんか取り払えばいいのにとずっと思ってきました。
だから平成7年に四津浩平さんから日本と中国の女子硬式試合の審判のお話をいただいたときは、『やったー』って飛び上がるくらいうれしかったですね。やっと女子も硬式野球ができる時が来たんだって」
今高橋は月2回、区立王子第三小学校に野球を教えに行っている。たった45分の授業ながら、子どもたちにマナーや用具を大切にすること、ボールの握り方、キャッチボールの仕方などを精いっぱい教えている。
「私にできることは野球しかありませんから、お声をかけていただけるなら生ある限りお役に立たせていただきたいと思っています。指導と言うのはおこがましいですが、75歳になってもグラウンド整備をし、野球をし、審判をする私の姿を見ていただくことが、あとに続く方々へのメッセージだと思っています。
今までたくさんの人たちに支えられてきたからこそ今の自分があります。同時に不良と言われても信念を曲げずにやってきたからこそ今の自分があります。自分の人生は自分のものです。やりたいことがあるなら、ぜひその思いを貫いてほしいと思います」

参考資料/『女たちのプレーボール』(風人社)、『女子プロ野球青春譜1950』(講談社)、『ハンカチ王子と老エース』(講談社)
60歳にしてアメリカの名門審判学校へ


43歳のときに、東京都の公認審判員になった高橋は、1997年、60歳のとき、セ・リーグの元審判部長、富澤宏哉の声がけで、アメリカの名門審判学校「ジム・エバンス審判学校」で学んだ。
同校は世界中の審判たちの憧れの的。向上心にあふれた高橋は、「どうしてもジム・エバンスで勉強したい」といって参加した。
「女に審判ができるのか」と野次られることが多かった時代。女性審判員の数もごくわずかだっただけに、おそらく高橋が日本で初めて同校で学んだ女性ではないだろうか。
※下の写真/一緒に学んだメンバーやインストラクターたちと。中央が高橋。




 エックスもぜひ
エックスもぜひ